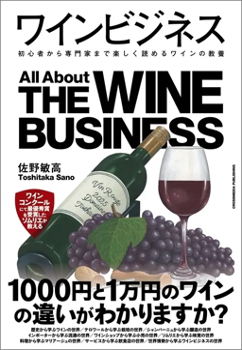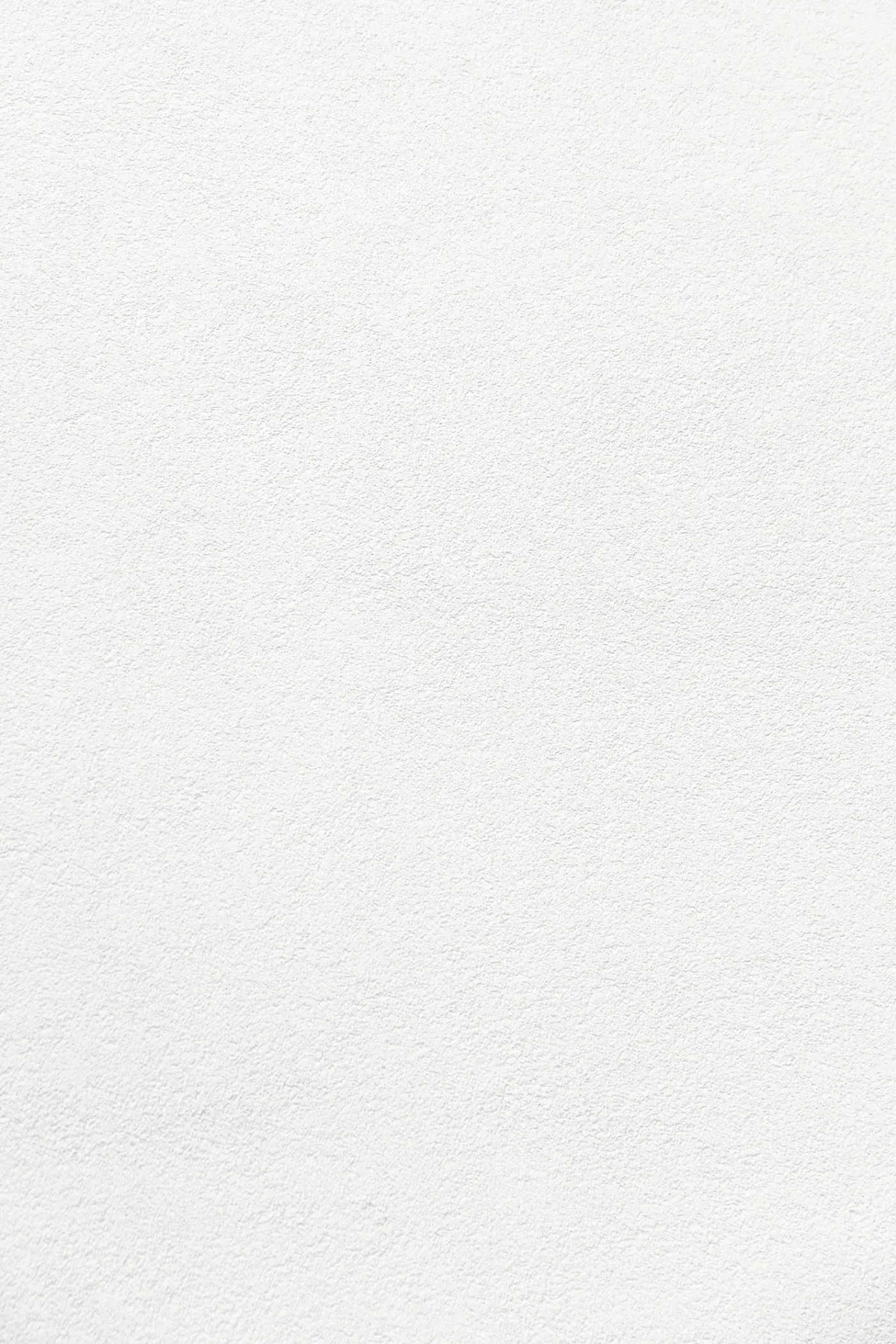「海に行きたくなる味」
「雨の日にぴったりな味」
「このワインはシャイ」
ワインの味わいを、決まった言葉で表現する必要はない。
そう語るのは、プロのソムリエであり『ワインビジネス』著者の佐野敏高さん。
佐野さんは、ワインを「商品」としてではなく、飲む人の記憶や感情をひらく“体験”として届けるために、自らの感性をとことん信じてセレクションを続けてきました。
11/11(火)、『ワインビジネス』の刊行を記念して、ライターの佐藤ゆみさんと佐野さんによる対談を青山ブックセンターにて開催しました。
書籍の制作秘話から、ワインを味わうための独自の感性、いま注目のワインまで。終始ワインへの愛と造詣の深さがうかがえる当日のお話をハイライトでお届けします。(以下敬称略)

「本気でワインを愛している人」に選ばれて
佐藤(司会)
ライターの佐藤友美です。私は『ワインビジネス』の執筆には関わっていません。佐野さんが経営するお店に9年間通ってきた、ただのファンです。あまりに素敵なお店で、初めは3日連続で訪れていたくらいです。コロナ禍を経た今は、1週間に1度の頻度になりました。今日はそのご縁で司会を務めさせていただきます。
佐野
皆さま、はじめまして。『ワインビジネス』の著者の佐野敏高と申します。東京・池尻大橋でレストランをやってまして、ワインの魅力をわかりやすく伝えることを大事にしています。
20年向き合ってきても、ワインは毎回表情を変える“理解しきれない不思議な液体”で、誰とどこで飲むかによっても味わいが変わります。それでもワインは人生を豊かにしてくれる相棒であり、僕にとっては愛らしい存在です。今日はよろしくお願いいたします!
佐藤
「ビジネスシリーズ」は『魚ビジネス』から始まりましたよね。以降20冊以上出版されていて、『ワインビジネス』もそのひとつだと伺っています。この本ができた経緯をお聞かせいただけますか?
佐野
クロスメディアの編集者の方が、フランスで「本気でワインを愛している人」を探していたそうです。その際、僕の名前が挙がったというのが最初のきっかけです。帰国後に、私の店でお話ししました。決め手になったのは私が「バゲットに金比羅ゴールドをのせて、赤ワインをどうぞ」とお出ししたこと。「面白い。この人と本を作りたい」と思われたそうです。
佐藤
「金比羅ゴールド」とは?
佐野
フランス料理の中で出していた金比羅(こんぴら)由来の食材です。ワインとは別の楽しみ方として、思考の死角から感動を与えるような体験になったのだと思います。
佐藤
書籍化に向けて、いつ頃から動き出したのですか?
佐野
昨年の7月頃ですね。執筆開始から発売まで約1年弱かかりました。
佐藤
出版業界の肌感としても、非ライターの著者が1年で刊行までたどりつくのは滅多にないスピードだと思います。執筆はどう進められたのですか?
佐野
深夜〜未明に1日2項目のペースで執筆して、約半年で本文の芯を通しました。 同時に目次を作って、各タイトルごとの中身もすり合わせました。
佐藤
執筆の過程で、目次づくりは一番ストレスが大きかったとお聞きしました。
佐野
書きたいことが多すぎたんです。削ぎ落としと配列にはかなり神経を使いました。
「ビジネス書っぽくない」文章を意識した理由
佐藤
本書の構成はどのように考えられたのですか?
佐野
“ビジネス”だけに寄ると、ワインが「高価なもの」という印象に固定されやすい。なので、「日常でワインを楽しむことがビジネスをする上での活力になる」という視点で書きました。
佐藤
文章が物語のように豊かで、「ビジネス書っぽくない」と感じました。
佐野
実は最初は、三島由紀夫を真似た文体で“おふざけ気味”に書いたんです(笑)。当然、それでは誰も読めないので、接客の話し言葉のリズムに切り替えました。
佐藤
佐野さんのお店に行ったことがある方はご存じだと思いますが、トイレに古い本がずらっと並んでいますよね。最近では素粒子の話が置かれていました。
佐野
ええ。手に取るだけで何かを感じていただけるような本を置いています。

ワインの味を自由で豊かに表現する
佐藤
佐野さんは、ワインの味や風景を「言葉にする」ことを大切にされていますよね。実際、どのように表現されているのですか?
佐野
約20年間、たとえ一日一行でも日記を書き続けてきました。もう30冊ほどになります。古い日本語や自分の感覚語彙を辞書から拾って、頭の中に「記憶の宮殿」として配置しておくんです。味→過去の体験→言葉へと橋をかけていくようなイメージです。
佐藤
本の中で、コルク栓をボトルから引き抜くことを「扉を開ける儀式」と表現されていますよね。また、「ワインにユーズドはない。一度きりの永遠」と書かれていました。
佐野
決まった言葉で表現することに抵抗があるんです。たとえば“青リンゴ”。
「海に行きたくなる味」、「雨の日にぴったりな味」、「このワインはシャイ」、「小鳥のさえずりが聞こえてきそうな味」——自分の言葉で表現して良いんです。伝わらなければ、「神社の湿った土」や「秋の金木犀」のように、お客様がわかる体験に翻訳します。
佐藤
(本をめくりながら)たとえば香りなら、「イギリスのアラビアンマーケット」、「南仏でドライブした時の乾いたハーブ」、「朝食のイチゴとヨーグルト」、「お爺ちゃんの家の古びたタンスや土壁」、「秋を連想させる金木犀の花」など、具体的な情景がたくさん挙がっていますね。
佐野
決まった言葉を味に当てはめてはいけません。みんなで飲むときも、先に“青リンゴ”と言って印象を固定しないこと。まずそれぞれの感覚を出し合ってから、必要であれば日常の体験に言い換えます。そのほうが、自由で豊かなコミュニケーションを楽しむことができるはずです。
毎朝決める、ワインの「スタメン」
佐藤
お店のグラスワインは80種類以上あるんですよね。9年間お店に通う私でさえ、同じワインが出てきたのは3回ほどしかありません。どう管理されているのですか?
佐野
毎朝、セラーに入ってワインに「おはよう」と言うことから始まります。その日の気温や湿度、お客様の層を想像しながら、「今日のスタメン」を決めています。同じワインでも、日によって表情が違う。 100点のワインも、50点のワインも、出し方や置き方次第で輝きます。僕の仕事は、ワインを売ることではなく「一番良い状態で出してあげる」ことなんです。

佐藤
“スタメン”は何本くらい決めるのですか?
佐野
20本前後ですね。 その日、開けておくワインを決めておくんです。あとはお客様の雰囲気を見ながら組み合わせていきます。
佐藤
最初の一杯はどのように決めているんですか?
佐野
「一口目の驚き」を大切にしています。 あえて、お客様のお気に入りのものとは別のワインを出すことがあるんです。お客様が苦手に思っていたタイプを好きに変えられることもあります。
ワインと「一体になる」感覚
佐藤
グラスの種類もたくさんありますよね。
佐野
20種類くらいあります。重いワインを小ぶりのグラスで“美しく縮める”こともあれば、軽いワインを大きめのグラスで“広げる”ことも。 グラスによって、香りの立ち方も、温度の変化も全く異なります。
佐藤
注いだあとは、必ずボトルの口を拭いていますよね。
佐野
儀式のようなものです。ワインは空気の触れ方で表情が変わるので、きれいに保ってあげたいんです。もし注いでみて納得できなければ、料理のソースに使うこともあります。
僕は、ワインを「対象として味わうもの」だとは思っていません。自分もその中に一緒に溶け込んでいくような感覚を抱いています。“正解当て”のような飲み方ではなくて、ワインと自分が一体になるように味わう。飲んでいるというより、一緒に泳いでいるように感じます。
佐藤
なるほど。言葉で聞くと、「ワインと一緒に泳ぐ」ことの意味がすごく伝わります。
佐野
味わいは、理屈じゃなくて身体の反応なんですよね。
感じる前に、もう感じている。 それをどう言葉にしていくかが、僕のテーマです。
品質の良いワインの見分け方
佐藤
家庭用に2,000〜3,000円くらいのワインを選ぶ場合、どこで買えば良いのでしょうか?
佐野
百貨店の専門ショップは安心ですね。スーパーマーケットでも買えますが、日が当たる場所に置かれていたり、長期にわたって陳列されていたりするものは避けたほうがいいでしょう。
佐藤
同じ畑、同じ銘柄でも味が異なることがあるのは、なぜですか?
佐野
輸送の温度や保管の状態が違うからです。インポーターがきちんと管理しているかどうかで、全く別物の味になります。ワインの状態は、誰が運んで、誰が扱っているかで左右されるんです。
僕は、生産者ときちんと関係を築いている人から買いたい。ワインの背景を理解していて、扱い方に愛がある。そういう方が携わったワインは、グラスに注いだ瞬間にエネルギーが違うんです。
佐藤
並行輸入のワインはどう選べば良いのでしょうか?
佐野
出所がはっきりしていないものは避けたほうがいいと思います。きちんとしたルートで、適切な温度で運ばれてきたものを選ぶべきです。割り当ての少ない銘柄などは、きちんとした扱いができる人にしか回ってこないんですよ。
佐藤
佐野さんは、 どうしてそんなに多くのグラスをご存じなのですか?
佐野
僕は酒販の免許を持っているので、インポーターから直接仕入れることも、酒屋を通して買うこともできるんです。そのおかげで、幅広いワインを試すことができます。毎日違うワインを出せるのも、その仕組みがあるからですね。

Q&A──ワインは「一度きりの永遠」
参加者
今、注目している産地はありますか?
佐野
チェコなどの中欧や、中国、台湾、そして日本ですね。古い文化と新しい挑戦が交差していて、とても面白いんです。
参加者
資格の勉強をしていると、“色→香り→味”と順に評価する癖がついてしまいました。
佐野
それはそれで大切な土台です。ただ、その先にある“自由さ”も大切。温度やグラスの形(三種類:細口・丸型・チューリップ)を変えて、同じワインの裏の顔を見てみるといいですよ。
参加者
ロマネ・コンティのような、“花束で頭を叩かれたような衝撃”を体感するにはどうすればいいでしょうか?
佐野
まずはブルゴーニュ・ルージュから飲んでみてください。地図アプリで畑を眺めながら飲むこともおすすめです。いつもとは異なる味に感じられることがありますよ。
参加者
家でのペアリングをもう少し上達させたいです。コツはありますか?
佐野
出汁を三種類(鰹・いりこ・昆布など)用意して、同じワインで合わせてみると面白いですよ。スパイス(カルダモン、花山椒など)を少し足したり、咀嚼の回数を変えたりしてみてもいいと思います。体の使い方を変えるだけで、ワインの印象はまったく違ってきます。
参加者
コンクールに出るような世界と、佐野さんのような“感覚的な表現”は矛盾しませんか?
佐野
知識はサービスの責任です。コンクールは旅の切符のようなもの。経験を積むと、お客様に還元できることが増えていきます。それは矛盾ではなく、両輪だと思っています。
参加者
ワインを嫌いになったことってあるんですか?
佐野
実はあるんです。資本主義的な“消費のスピード”に疲れてしまった時期があったんです。でも、ナチュラルワインに出会い、その“やさしさ”に泣いてしまいました。
ワインは「一度きりの永遠」。 同じ状態のものは、二度とありません。だからこそ、また好きになれるんです。
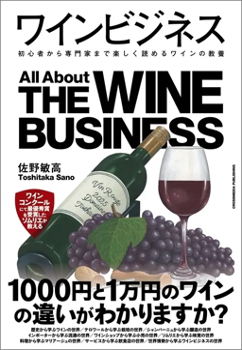
【書籍情報】
著者:佐野敏高
定価:1,738円(本体1,580円+税)
体裁:四六判/272ページ
ISBN:978-4-295-41098-0
発行:株式会社クロスメディア・パブリッシング(クロスメディアグループ株式会社)
発売日:2025年6月3日
【プロフィール】
佐野敏高(さの・としたか)
1984年神奈川県横浜市生まれ。幼い頃マレーシアで育ち、高校卒業後ニュージーランドへ留学。ワインのある生活に魅せられイギリスへと拠点を移す。ヨーロッパ各国へ足を運びワインを学ぶ。帰国後は老舗グランメゾンのアピシウスなど、さまざまなフレンチレストランやワインバーで経験を積む。
株式会社Racinesなどに勤めたのち、2016年に独立。Wine Bistro calmeとワインのお店 さらさを開業。オーストリアワインアンバサダー。ポルトガルワインコンクールにて最優秀賞受賞。趣味はフルート演奏と日本舞踊。
佐藤友美(さとう・ゆみ)
1976年北海道知床半島生まれ。テレビ制作会社勤務を経て文筆業に転向。元東京富士大学客員准教授。
さとゆみビジネスライティングゼミ主宰。卒ゼミ生によるメディア『CORECOLOR』編集長。
書籍ライターとして、ビジネス書、実用書、教育書等のライティングを担当する一方、独自の切り口で、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆している。
著書に『女の運命は髪で変わる』(サンマーク出版/17刷)、『書く仕事がしたい』(CCCメディアハウス/6刷)、『髪のこと、これで、ぜんぶ。』(かんき出版/7刷)子育てエッセイ『ママはキミと一緒にオトナになる』(小学館/2刷)など。
▼採用情報
クロスメディアグループでは、共に働く仲間を募集しています。詳しくは当社の採用サイトをご覧ください。
→https://recruit.cm-group.jp
『ワインビジネス』
1,738円(本体1,580円+税10%)円
Amazon.co.jpで購入する