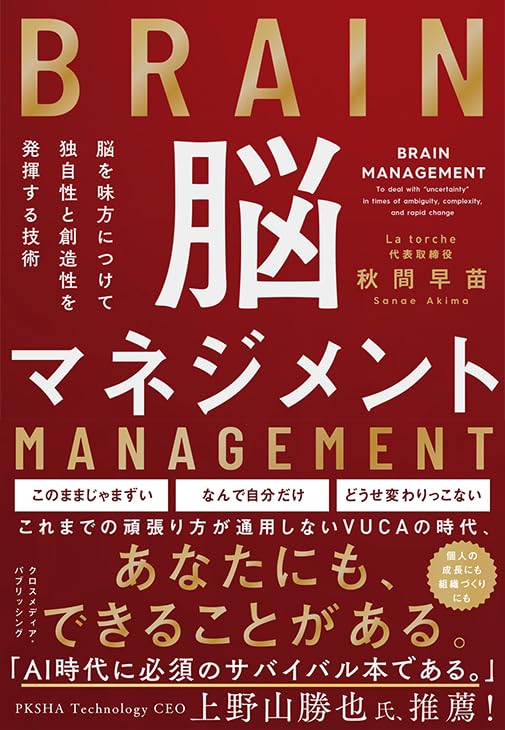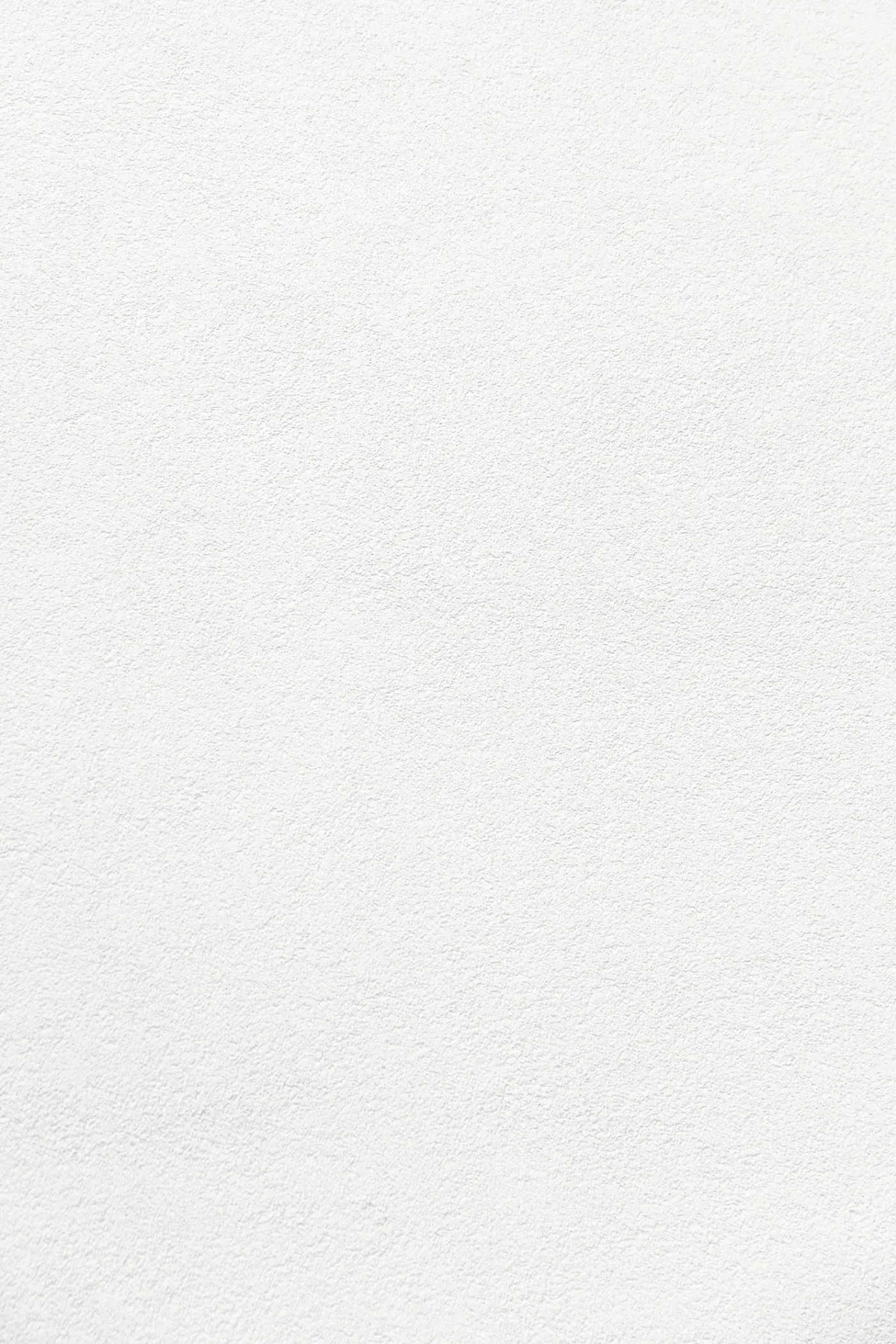2024年12月10日に、新刊『脳マネジメント〜脳を味方にして独自性と創造性を発揮する技術〜』(クロスメディア・パブリッシング)の発売を記念したトークライブイベントが開催されました。
第一部では、著者の秋間氏が「なぜ今、脳マネジメントが必要なのか?」について解説。第二部は、「個性を活かして、これからの時代を共創する方法」をテーマに2人のゲストをお招きしての鼎談が行われました。第三部はトークの学びを深めるための交流会。40名以上が参加し、大盛況のイベントとなりました。
【第一部 秋間氏トーク】
ほっとするための技術を道具箱に

第一部は、著者である秋間氏のトーク。秋間氏が繰り返したのは、「カチコチからイキイキへ」という言葉でした。人間には、脳がカチコチに固まっている状態と、イキイキとほぐれている状態がある。新しいことをしようとするときなど、思考や気持ち、身体が縮こまっている「カチコチ」の時、「どうしようもない」と考える人が多いと言います。
イベントの冒頭では、「カチコチ」をほぐすため、参加者同士の雑談の時間が設けられました。秋間氏は「カチコチになったときに、何もできないと諦めるのではなく、自分の状態に気付く力や、ほっと緩み互いにイキイキするための技術を皆さんの道具箱に入れていただきたい」と参加者にメッセージを送りました。
脳は自分が知らないうちに動き回る暴れ馬

秋間氏は、著書の中で脳を「暴れ馬」に例えます。本人の意図を無視して、勝手に動きまわり、人間は知らないうちに脳に振り回されている。また、人間が認識している脳の働きは一部だけであり、大部分は意識できていないと解説します。
トークの中では、脳の働きを現代に合わせて捉え直す必要性を語りました。「言葉や行動、身体の動きといった表面に現れる部分は氷山の一角に過ぎず、水面下には膨大な思考や感情が隠されています。さらに、見えないものを探るにはエネルギーが必要で、省エネで動こうとする脳にとっては扱いにくい領域です。脳の暴走に振り回されている時は、氷山の一角しか見ていない状態。
しかし現代社会においては、氷山モデルの水面下にあるものが重要視され、例えばSDGsといった概念は、社会や環境といった数値化しにくい要素も考慮する必要があります。目に見えるものや数値化できるものだけにとらわれていた私たちの世界観は変わりつつあり、氷山全体を捉える重要性が認識され始めています」
【第二部 秋間氏・嘉村氏・吉川氏鼎談】
「ありがとう」で感じる喜び

ゲストの紹介の後、秋間氏は、時代による経済やビジネスシーンの変化と、そこで求められる考え方について2人に尋ねました。
吉川氏は時代の移り変わりがビジネスにも影響を与えていると指摘。「昔は、良い車や良い家を手に入れることを目的に働く人がほとんどだった。しかし現代の若者に物欲はあまりなく、SNSなどで『見てもらいたい』という承認欲求を強くもっている。そこからさらに時代は変化し、どれだけ『いいね』を貰えるかから、どれだけ『ありがとう』を言ってもらえるかが、これからの価値になっていくのではないか」と未来を探ります。
秋間氏はこれに共感。「機械論的世界観と生命論的世界観は、ティール組織でも脳マネジメントでも大切な二つの軸になっている。『ありがとう』で喜びを感じる私たちは、一人ではなく周囲と響き合って生きている」と応えました。
一人ひとりの感性を尊重する

嘉村氏は、「今後は画一的な形式ではなく、それぞれが個性をもった人間らしく彩りのあふれる経済活動に時代が移り変わっていく」と述べました。オランダの訪問看護組織「ビュートゾルフ」を例に挙げ、「トップではなく、現場で働く看護師たちに裁量権があり、居心地の良い空間や雰囲気を作り上げる。そのように、個人が創意工夫することに対する恐れを取り払えば、一気に彩りがあふれ、余裕のある職場になる。そして、余裕が生まれたぶん、お客様を幸せにすることができる」と語ります。
秋間氏は、一人ひとりの個性に対応するには、膨大なリソースが必要だとしながらも、「あまりにも個性を無視してしまうと生きづらい世界になってしまいます。画一的にアップデートしていくのではなく、一人ひとりの感性を尊重する居場所づくりといった温かみのある取り組みこそ、未来の可能性を広げることができるのではないでしょうか」と強調しました。
新しい時代に対応するために

続けて秋間氏は、著書の中から「無自覚の自覚」というキーワードを挙げました。「無自覚な状態が続けば、現在の価値観から乖離します。しかし、幸いにも変化の必要性を私たちは気づき始め、このままではいけない、本当にやりたいことができないという感覚は、すでに多くの人が共有しているのではないでしょうか」と投げ掛けます。
吉川氏は、自身の経験から打開策を示しました。「現状を打破し、未来へと移り変わるためには、目標までのリスクや壁を利用すること、そしてまずはやってみることです。自分はベンチャー立ち上げ時にクライアントから受けたダメ出しを合格基準と捉え、目標達成への近道に気づきました。ネガティブは成長のチャンスであり、ポジティブへの変化のきっかけ、課題解決のヒントは自分の中にあると捉えることで、どんな壁にぶつかっても次なる一手が見えてきます」とポジティブな視点の重要性を語ります。
嘉村氏は、北野唯我氏の著書『天才を殺す凡人』をもとにヒントを提示。「世の中には秀才タイプ・天才タイプ・凡人タイプがいます。現代は秀才タイプが出世しやすい仕組みになっていますが、共感性溢れる凡人も社会的価値を生み出すことに挑戦する天才を生かせるような仕組みをつくっていくべきです。そうすることで、より良い社会へ移り変わっていくことが可能なのではないでしょうか」と論じました。
第二部の最後に、秋間氏はトークを振り返りました。 「この場が、個性を活かしてこれからの時代を創るための手段の一つです。今日のイベントに誰一人として、同じ人はいません。そして舞台上と客席で、上も下もありません。色々な視点からの意見が交わされたからこそ、単一の視点では感じ取れなかった感覚を皆さん体感できたのではないでしょうか」
同じ人と話し続けてはいけない交流会

第三部では、交流会が行われました。ルールは「ずっと同じ人と話さない」。秋間氏はその意図を「カチコチにするためではなく、イキイキするための誘い」だと説明します。
「皆さんの違いを味わったり面白がったりする。それをベースに交流会を過ごしていただきたいので、なるべく話したことがない方と話してください。面白がるスイッチが入れば、楽しむ自分を発見できると思います。その感覚を持ち帰るための時間です」。参加者はイキイキとコミュニケーション。盛況のままにイベントは終了しました。
【登壇者プロフィール】

秋間 早苗(あきま・さなえ)
株式会社La torche(ラトルシェ)代表取締役
2005年、東京大学農学部卒業。
在学中よりサステナビリティや国際協力に関心を持ち、2007年に国際学生サミットを主宰。
前例も正解もない、ゼロからプロジェクトを立ち上げる経験を通じて、自身の創造力を最大限に発揮できる領域を見出し、2008年に同大学大学院国際協力学を修了後、起業の道を選ぶ。産官学連携プロジェクトや多分野にわたる事業開発をリードしながら、事業性と社会性の融合、マルチステークホルダーの共創関係構築に取り組む。
2017年、結婚と出産を経て株式会社La torcheを設立。これまでの経験と領域横断的な知見を基に、独自のアプローチ「脳マネジメント」を打ち立て、個人や組織がその「存在ならでは」の価値を最大限引き出すための支援を行っている。国内外の現場で培った人間理解に基づき、持続可能な未来を志向した人材育成と組織づくりを目指し、積極的に発信を続けている。 カナダ・バンクーバー在住。2児の母。

嘉村賢州(かむら・けんしゅう)
ベストセラー『ティール組織』(英治出版)を日本に広めた第一人者。
場とつながりラボhome’s vi代表理事/株式会社令三社取締役 2008年にhome’s vi設立。
当時はまちづくり(京都)や組織開発ファシリテーターとしての活動が中心だったが、1年間のサバティカル休暇をきっかけにティール組織をはじめとする進化型組織の研究や普及に主軸を移す。現在は「未来の当たり前を今ここに」をテーマに、進化型組織関連の活動に加え、北海道美瑛町のまちづくり支援に携わっている。
2023年に進化型組織の情報メディア「ティール組織ラボ(teal-lab.jp)」をオープン。
2023年に第一子が生まれたことをきっかけに、大幅に活動を制限し、家族中心で子どもから生き方を学ぶ生活にシフトしようとしている。

吉川登(よしかわ・のぼる)
花キューピット株式会社 代表取締役社長。1965年生まれ。大阪府出身。
大学卒業後、総合商社やITベンチャー企業を経て2004年、動画などの処理技術を提供するベンチャー企業を起業し、2006年に東証マザーズ上場。さまざまな企業のメンターやエンジェル投資家を経て、2015年に花キューピット株式会社常務取締役、2016年取締役社長に就任し、2019年より現職。花キューピットグループでは、全国約4000店舗のネットワークで注文先に近い花屋が花を届け、CO2排出削減に貢献している。
▼採用情報
クロスメディアグループでは、共に働く仲間を募集しています。詳しくは当社の採用サイトをご覧ください。

『脳を味方にして独自性と創造性を発揮する技術 脳マネジメント』
1,738円(1,580円+税10%)円
Amazon.co.jpで購入する