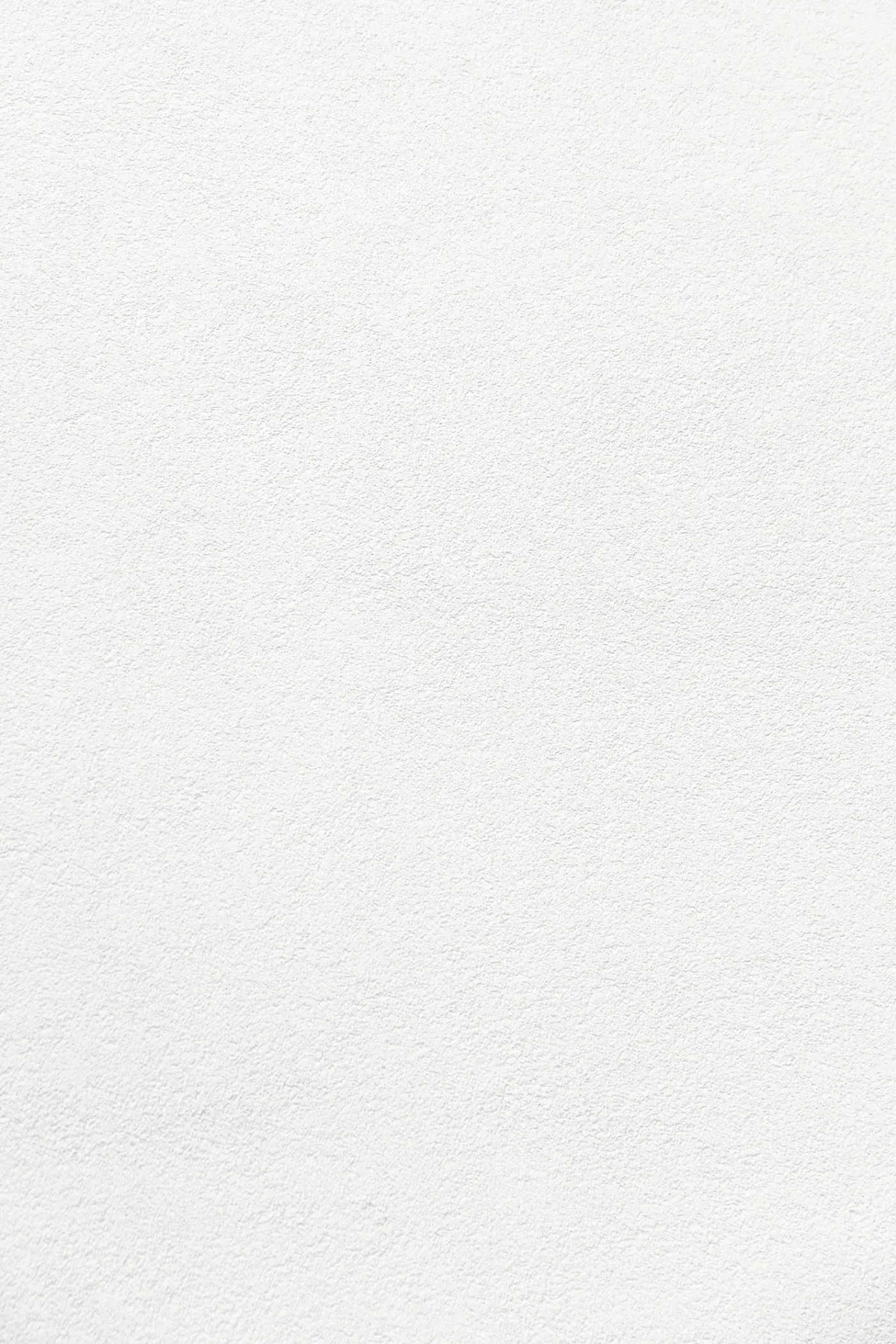シリーズ累計1,400万部を超える世界的ベストセラー『人生がときめく片づけの魔法』(近藤麻理恵著、サンマーク出版)を筆頭に、数々のヒット作品を手掛けてきた、エリエス・ブック・コンサルティング代表取締役の土井英司さん。新基準を見出すヒアリングと、自然発生する人脈を見据えたブランディングで、独自の出版プロデュースを展開してきました。
「言葉が市場をつくり、ビジネスにインパクトを与える新たなカテゴリーを確立する」。土井さんが編集において何を重視しているのか、クロスメディアグループ代表取締役の小早川幸一郎との対談でお届けします。
「編集」の役割は、書籍や動画を作ることにとどまらず、「人と企業の編集」「事業の編集」「社会の編集」へと広がっていく。本シリーズでは、編集者でありクロスメディア・パブリッシングの代表でもある小早川幸一郎が提唱する「編集4.0」をテーマに、編集の持つ価値をゲストとともに拡大していきます。
編集4.0とは・・・・
編集1.0:メディアの編集
編集2.0:人の編集
編集3.0:事業と企業の編集
編集4.0:社会の編集
※編集4.0の定義はこちら▼
『【編集4.0:Vol.0.0】編集とは、すでにあるものを組み合わせて新しい価値を生み出すこと』

慶応義塾大学総合政策学部を卒業後、ゲーム会社を経て編集者・取材記者・ライターとして活躍。2000年にアマゾンの日本サイト立ち上げに参画し、数々のべストセラーを仕掛けるカリスマバイヤーとして名を馳せる。2004年に独立後は、シリーズ累計1,400万部を超える世界的ベストセラー『人生がときめく片づけの魔法』をはじめ、ビジネス書、実用書を中心に出版プロデュース事業を展開。ビジネス書評家としても活動し、著書はロングセラー多数。

出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、デザイン事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開。
悩みと不満の数だけ市場がある
小早川 私がこんまり(近藤麻理恵)さんを知ったのは、エリエス・ブック・コンサルティングの『10年愛される「ベストセラー作家」養成コース』の卒業プレゼンテーションの審査員として参加したときです。彼女は当時20代前半で、片付け好きな元気な営業女子という印象でした。それがいまや「世界のこんまり」になっているのは、土井さんの「人を編集する力」を象徴していると思います。
土井 人の編集と、他の分野の編集との違いは、その過程で自然とネットワークが生まれていくことだと思っています。「人」を編集するうえでは、その過程全体を通して生まれる人脈を予測してブランドをつくる必要があります。
その人の口癖やファッションなど、好んでいるものから価値観を把握し、「こういう人たちを惹きつけるだろう」と、読者層を予測します。つまり、すごく失礼ながら『人生がときめく片づけの魔法』は、「人生にときめいていない人」がターゲットなんですよ。
物だけではなく、人間関係のしがらみを感じている人。本当は捨てたいのに心理的なバリアがあって捨てられずに悩んでいる人たち。そんな人たちへの本なんです。かつてのこんまりさんも同じだったからこそ、多くの人の共感が生まれました。
読者と同じ悩みを抱えた経験があって、それをクリアした人の本は売れる。でも、クリアしたからといって読者の気持ちを理解できなくなると、途端に売れなくなってしまいます。読者と同じ視点で悩みや課題を持ち続けられる人は、本当にすごいですよね。
小早川 「ときめき」のように、著者がポロッとこぼした何気ない言葉から、未来まで予測してプロデュースするための秘訣はあるんですか?
土井 秘訣というほどではないですが、ぼくが他の人とちょっとだけ違うのは、「人間の表情」にすごく興味があるところだと思っているんです。

たとえば東京の地下鉄の通路を歩いていて、通勤ラッシュで大勢の人とすれ違うとき、全員の顔を見てしまうんです。「これから会社に向かうのに、こんな表情をしているってことは、仕事に不満があるのかな」とか、いろいろ想像するのが、いやらしいぐらい好きなんですよ。
ぼくは、自分の本音に従って生きている人は、ほとんどいないと思っています。そしてそんな状態を変えたいと願って、人は本を読む。だから人の悩みや不満の数だけ市場があると考えています。
小早川 人に興味関心を持つことが、土井さんが人を編集する際のベースになっているんですね。
土井 そうだと思います。みんな本当はやりたいことがあって、ありたい姿があるんだけど、なかなかその通りにはできないですよね。自分の生きたいように生きたくて、もがいている方を応援したいというか。「本当はこうしたいんでしょう」と、本を通じて背中を押したいと思っています。
数と技術で変化する「伝え方」の最適解
小早川 Amazonは物流やテクノロジーの会社ですが、土井さんはAmazonにいたころから「人間」と向き合っている感じがしていました。
土井 テクノロジーは、人間の真実を教えてくれることもあります。
Amazonには「よく一緒に購入される商品」が表示される機能がありますよね。ユーザーはそれを確認できるので、データから人間の思考タイプの傾向が見えてきます。
たとえば、ロボットをつくるキットとAIの本は、一見関係なさそうに見えても「自分で何かをつくって動かしてみたい」というニーズで結び付いています。逆に、Aというアイドルの商品を買う人は、Bというアイドルの関連商品は買わないということもわかります。
すると、テクノロジーを通じて意外なニーズや人間らしさが見えてきて「人間って愛おしいな」と思えてきます。そういう瞬間が好きでしたね。
小早川 土井さんは人間らしさを大事にしている一方で、テクノロジーへの関心も強くて、常に新しいメディアやコンテンツをビジネスに活用していますよね。テクノロジーの進化や普及は、「人の編集」にどう影響していると思いますか。
土井 メディアによって表現形態が変わるので、テクノロジーの進化によって個人に求められる素養も変わってきます。最近は話し方に関する本がベストセラーになっているように、メディアの特性に合わせた話し方、伝え方が特に重要になってきているのを感じますね。
伝え方は、発信者の数と受け手の数の比率でも変化します。テレビには芸能人がいっぱい出演していて、発信者が複数いますよね。それに対して受け手は、リビングなどで家族がそろって見るシーンを想定してつくられています。もちろんひとりで見るケースもあると思いますが、基本的に複数から複数へ伝えることを前提にしたメディアです。
ラジオの発信者はパーソナリティとアシスタントの体制に対して、聞き手はひとりというパターンが多いでしょう。
本は、完全に一対一です。一対一だと、すごく真面目な話もできます。テレビだと、番組によっては「なに真面目な話をしてんだよ」なんて、ちょっと茶化されたりする場合もあります。
いまはテレビよりYouTubeを見る人も多くいますが、YouTubeとテレビの違いは、画面の開き具合です。スマホで見るときはテレビほど画面がオープンにならず、受け手がひとりの場合が多いですよね。基本的にはパーソナルだけど、他人にチラ見されても許されるレベルのコンテンツのほうが人気が出る傾向があると思います。
今後さらにイヤホンやWEB技術が進化すると、スマホで発信するメディアはどんどんパーソナルな世界に入っていきます。すると求められるコンテンツの性質も変化していくでしょうね。
素材を最大限に生かす、得意領域での分業
小早川 人数によって発信内容や伝え方が変化するという話は、すごく面白いですね。そういった人と差をつける考え方はどうやって養っているんですか?
土井 ぼくには小早川さんのような編集力はないので、いい素材を見つけるために時間と手間は惜しまないようにしているだけです。

ちょっと気になる人がいたら現場に足を運ぶことをモットーにしていて、片道1000キロ以上の距離でもすぐに車で行きます。すると、パソコンの前に座って考えているときとは違う見方ができるんですよ。
たとえば能登に行って知ったのは、ボランティアには65歳以上の人がたくさんいるということ。仕事をしていないと社会とのつながりが失われがちな年代ですが、ボランティアをすれば人の役に立てるし、社会貢献もできて、ボランティア同士で新たな人間関係もできます。かかるお金は交通費くらいなので負担も少ないし、全国各地へ行くので、その土地ならではの経験をしたり、名物を食べたりできる楽しみもあります。
現場だからこそ見えることや聞ける話があるので、それを大事にしているんです。そうした素材を見つけた後は、編集者と一緒に本をつくる。これがぼくの基本的なやり方です。
小早川 土井さんが「いい素材があるからうまく料理して」とクロスメディアに卸してくれるような関係が、もう20年以上続いてきました。人の編集において、それぞれ得意なことが違うから、私たちはいい関係を続けられているのかもしれませんね。
土井 ぼくは「自分の苦手なことには口を出さない」というポリシーがあるからこそ、うまく人とコラボできているんだと自認しています。
役割としては、ぼくが魚屋なら、編集者は料理人です。魚屋は新鮮な魚を仕入れて、この魚がどんな食感でどんな味なのかを料理人に説明する。料理人はそれを受けて、お客さんの好みに合わせた調理法や盛り付け方を考える。必要な能力も、やるべきことも違います。
料理人が海に行って一本釣りをするケースもありますけど、効率が悪いですよね。だから、一番上手に料理してくれる人に最高の素材をパスする役割として、ぼくの会社をつくったんです。
小早川 自分の得意な領域を理解しているからこそ、分業的なスタイルを取り入れているんですね。

土井 もし大間のマグロみたいな素材があれば、料理したがる人は多いでしょうね。でも、誰でも料理できるわけではありません。その素材を最大限に生かせる編集者が必ずいるんです。
学習書の場合、希望する大学に行けなかった経験を持つ編集者に依頼すると、読者の悔しさや課題を理解しているので売れる本ができます。「読者が共感できる視点」と「本を出す動機」の2つを持つことは、編集者にとってとても大事な素養だと思います。
日本のコンテンツを世界基準に編集する
小早川 編集や出版という領域で、今後挑戦していきたいことはありますか?
土井 会社としては今後もいい素材を見つけて、人を編集して、新たな市場を生み出す出版プロデュース事業を頑張っていきたいと思っています。
いま特に注力しているのが、最近立ち上げた「Smartbooks」という会社の事業です。ビジネス書を耳で聴けるオーディオブックをつくれるアプリを開発しており、いままでオーディオブックが存在しなかった人気のビジネス書も聴くことができるようにしています。
そのうちやってみたいのは、ビジネス書をまるごと自動翻訳する機能です。AIナレーターがビジネス書をまるごと自動で翻訳してくれて、出版社がわざわざ英語版の本をつくり直さなくても海外へ展開できるようになるといいですね。
隙間時間に学びたい人や、ビジネス書をもっと読みたい人に日本の優れたコンテンツを届けたい。そして海外に向けても提供していくことで、出版業界に貢献していきたいと思っています。
▼採用情報
クロスメディアグループでは、共に働く仲間を募集しています。詳しくは当社の採用サイトをご覧ください。